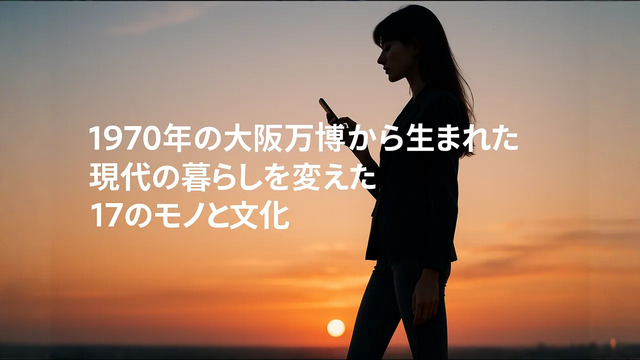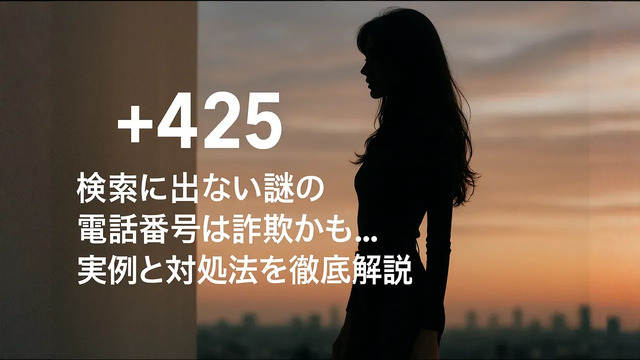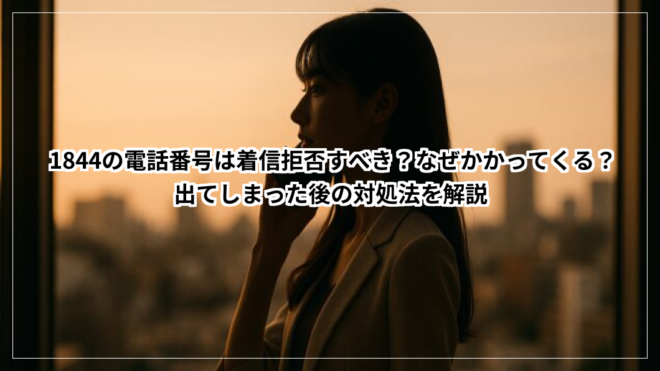あの1970年の大阪万博をきっかけに広がったものとは?
スマートフォンやビデオ通話、ブルガリアヨーグルトや回転寿司など、今の私たちの暮らしに欠かせないモノや文化の数々が、実は万博から始まっていたのです。
この記事では、1970年の大阪万博を起点に実現・普及した技術やサービス、文化について、当時のエピソードを交えながら詳しくご紹介します。
2025年の大阪・関西万博にもつながる“未来の原点”を知ることで、これからの社会のヒントがきっと見えてきますよ。
読み進めるうちに、「えっ、あれも万博からだったの!?」と驚く発見があるかもしれません。
ぜひ最後までお楽しみください。
1970年の大阪万博をきっかけに広がったもの
1970年の大阪万博をきっかけに広がったものについて解説します。
①スマートフォンとビデオ通話の原点
1970年の大阪万博で一般公開された「ワイヤレステレホン」は、まさに現代のスマートフォンの先祖といえる存在でした。
このワイヤレステレホンは、電電公社(現在のNTT)が出展した電気通信館にて展示されたもので、コードレスで通話できることに多くの来場者が驚いたそうです。
また、ビデオ通話の原型となった「テレビ電話」も万博会場で活躍しました。
特に、迷子センターでは親子がテレビ電話で再会する様子が話題となり、未来のコミュニケーションのあり方を体感できた貴重な経験となりました。
これらの技術は、その後の携帯電話、スマートフォン、さらにはZoomやLINEビデオ通話など、現代のオンラインコミュニケーションへと繋がっていったのです。
まさかあの時、巨大な装置だったテレビ電話が、手のひらサイズになる日が来るなんて、当時の人々は想像もしていなかったでしょうね。
私も取材で当時の映像を見ましたが、来場者の目がキラキラしていて、本当に感動していた様子が伝わってきましたよ~!
②ピクトグラムが日本中に広がる契機
ピクトグラム、つまり「絵文字のような案内標識」も、1970年の大阪万博で一気に注目される存在となりました。
もともとは1964年の東京オリンピックで導入されたデザインですが、実はその時はまだ統一されておらず、視認性に欠ける面もありました。
大阪万博では、デザイナー福田繁雄氏の手により、統一されたピクトグラムがパビリオンや施設内に配置され、「誰にでもわかるサイン」として高く評価されました。
言葉の壁を超えて情報を伝える手段として、ピクトグラムは世界中の人々に「わかりやすさ」の大切さを教えてくれたのです。
この経験が後の日本社会でも生かされ、駅や空港、公共トイレ、病院など、あらゆる場所での案内表示にピクトグラムが広まりました。
2021年の東京オリンピックでも大きな話題になりましたが、そのルーツが大阪万博にあるというのは驚きですよね!
今では当たり前の存在ですが、万博という大舞台で「標準化」と「見える化」を先取りした点が素晴らしいな~と感じます。
③ブルガリアヨーグルトの誕生秘話
今や日本の朝食に欠かせない「ブルガリアヨーグルト」。
この製品も、実は大阪万博がきっかけで誕生したんです。
当時のブルガリア館では、本場ブルガリアのプレーンヨーグルトがふるまわれていました。
それまでの日本では、甘いフルーツヨーグルトが主流で、酸味の強い本場の味は珍しかったんですね。
これに感激した明治の社員が、「この味を日本にも広めたい」と強く感じたことが、ブルガリアヨーグルト開発の第一歩になりました。
その後、ブルガリア政府との交渉を経て、「ブルガリア」という名称の使用許可を得ることに成功。
3年かけて試行錯誤の末に商品化されたこのヨーグルトは、日本中で大ヒットとなりました。
実は今も、あのときのパビリオンのロゴが、製品パッケージのデザインに取り入れられているんですよ。
ほんと、大阪万博って、単なるイベントじゃなくて、日本の食文化にも新しい風を吹き込んでいたんですね!
私もブルガリアヨーグルト、朝ごはんでよく食べてます~。あれが万博から生まれたと思うと、感慨深いです!
④動く歩道とエアドームの画期的技術
大阪万博の会場では「未来の乗り物」や「未来の建築」が体験できる技術が、いくつも実装されていました。
その代表格が、動く歩道とエアドームです。
動く歩道は、会場の移動効率を向上させるために設置され、乗っているだけで遠くのパビリオンへスムーズに移動できるという画期的なものでした。
実は、梅田の阪急電鉄駅には既に設置されていたものの、全国的にその便利さが認知されたのは、この万博をきっかけにしてからです。
さらに、空気の圧力だけで屋根を支えるエアドームも注目されました。
アメリカ館や富士グループ館で採用されたこの構造は、後の東京ドームに受け継がれ、現代の大規模スタジアムの建築にも影響を与えています。
空気で膨らむ建築物は、省資源・短期間での建設が可能という点から、サステナブル建築としても再評価されています。
「空気で支える建物」という未来感が、50年を経た今もなお斬新に感じるのは、それだけ当時が先進的だった証拠ですよね。
私も大阪万博の写真を見るたび、タイムマシンに乗ってみたい気分になります~!
⑤電気自動車・リニアモーターカーの初披露
今でこそ街中を走る電気自動車も、1970年当時は夢のような存在でした。
大阪万博では、会場内の移動手段として電気自動車と電動アシスト付き自転車が実際に運用され、来場者は未来の乗り物を間近に体験できました。
また、日本館ではリニアモーターカーの模型展示とともに、実際に短距離を走行するデモンストレーションも行われ、大きな注目を集めました。
「時速500kmで東京と大阪を結ぶ」夢の構想は、まさに未来を象徴する存在でした。
残念ながらリニア中央新幹線の本格開通はまだ実現していませんが、1970年の展示がその技術の発展に寄与したのは間違いありません。
電気で走るクルマや磁力で浮いて走る列車――当時の子どもたちにとっては、まるでSF映画の世界に入り込んだような体験だったことでしょう。
今やその子どもたちが、自らリニア開発の現場で働いているかもしれないと思うと、夢のリレーって素敵ですね!
⑥ウォシュレットや電波時計も登場
「清潔で快適なトイレ文化」を根づかせた技術のひとつが、ウォシュレットです。
大阪万博では温水洗浄便座が紹介され、その快適さと衛生性が話題を呼びました。
それまでの日本では、トイレといえば「我慢」のイメージが強かったですが、この展示を機に、トイレ空間への意識がガラリと変わりました。
その後の開発と改良を経て、TOTOなどが商品化。今や世界でも大人気の商品となっています。
また、電波時計の登場も万博がきっかけでした。
セイコーが展示した世界初の電波時計は、原子時計と連動して自動で時刻を調整するという、まさに「時間の革命」とも言える技術です。
会場の巨大な時計塔では、秒単位の正確な時刻を示しており、多くの来場者が「未来の時間」を感じたことでしょう。
どちらの技術も、生活の質そのものを底上げするものであり、万博の「暮らしに役立つ未来技術」というテーマにぴったりでしたね。
ウォシュレットの快適さに慣れた今の生活を思うと、1970年の展示には感謝しかありません!
⑦ファストフードと缶コーヒーの普及も後押し
今では当たり前のように街中にあるファストフード店や缶コーヒーも、1970年の大阪万博が普及のきっかけとなりました。
まず注目すべきは、ケンタッキーフライドチキンの日本初出店。
万博会場でアメリカンパークに登場し、来場者に提供された本場のチキンは、「日本の味覚」に衝撃を与えました。
また、同時期に日本へ進出したマクドナルドやミスタードーナツなども、万博の集客効果で一気に知名度を上げました。
そしてもうひとつ、日本人の味覚に深く浸透したのが、缶コーヒーです。
UCCが世界で初めて缶コーヒーを販売したのは万博の前年ですが、会場で多くの人にふるまわれたことで一気にブレイク。
今ではコンビニや自販機で当たり前に手に入る缶コーヒーですが、当時は「飲みやすい!」「便利!」と大好評でした。
「甘い缶コーヒーを片手に、おにぎりを食べた思い出が忘れられない」という証言もあるほど、味覚の記憶に残る体験だったようです。
まさに、食と飲み物が未来のライフスタイルを変えた瞬間だったんですね!
万博を機に実現・普及した文化やサービスまとめ
万博を機に実現・普及した文化やサービスについて、代表的なものを詳しくご紹介します。
①回転寿司が人気ジャンルとして定着
今や全国どこに行っても見かける「回転寿司」。そのルーツが、実は1970年の大阪万博にあったことをご存じでしょうか?
当時、万博会場のモノレール西口駅前に出店した「廻る元禄寿司」が大盛況を博し、「ベルトコンベアで寿司が流れてくる」というユニークな仕組みに、多くの来場者が目を輝かせました。
この体験が強烈なインパクトを与え、回転寿司はただのトリックではなく、「誰でも気軽に寿司を楽しめる新しい食文化」として広がっていったのです。
しかも、この「寿司を回す」という発想が、日本の食を世界に広めることにもつながりました。
今ではアメリカやヨーロッパ、アジアなど各国でも回転寿司チェーンが展開され、日本発のグローバルなビジネスモデルとしても評価されています。
筆者としても、回転寿司は子どもの頃からのワクワク体験のひとつ。あのレーンを流れる寿司を見ると、今でもちょっとテンション上がっちゃいますよね!
②シャチハタの普及とスタンプラリー文化
今ではビジネスでも家庭でも当たり前に使われているシャチハタのスタンプ。
この便利な「インクいらずのはんこ」も、1970年の大阪万博での使用がきっかけとなって、広く世間に知られるようになったんです。
当時の万博では、各パビリオンに設置されたスタンプラリーが大人気で、来場者が持参した台紙にスタンプを押して回るという文化が生まれました。
そのときに活用されたのが、インクを付けずにポンと押せるシャチハタ印だったんですね。
この体験から「子どもも大人も楽しめるイベントアイテム」としてのスタンプラリー文化が浸透し、現在では観光地や商業施設、さらには駅スタンプやアニメのコラボイベントでも定番化しています。
そして、ビジネスシーンでもシャチハタが「押印の時短ツール」として評価され、今では多くの企業で日常的に利用されています。
ちょっと地味だけど、万博がきっかけで「日本のはんこ文化」に革命が起きたのは間違いありませんね~!
③LANネットワーク導入が社会に与えた影響
大阪万博は、技術面でも多くの革新を社会に届けましたが、中でも特筆すべきなのがLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)の導入です。
当時、会場内での運営効率を高めるために、大規模なコンピュータシステムが設置され、迷子管理や駐車場の空き状況の把握などに使われていました。
なんとこのネットワークシステムの構築には、設備費31億円・運用費4億円がかかったというから驚きです。
そしてその仕組みが「人と情報を繋ぐ」ことの重要性を社会に知らしめ、後のオフィスコンピューティングやネットワークインフラ構築の土台となったのです。
当時の迷子人数は4万人以上、大人の迷子も10万人以上と、まさに「ITなしには捌ききれない規模」。
LANがその管理を支えたことで、ITの価値がリアルに証明された瞬間でした。
現代のスマートシティやIoTの源流をたどると、1970年の万博に行きつく――そう思うと、あの時代の技術者たちに感謝したくなりますよね。
「迷子管理で未来を創る」…ちょっとカッコよすぎません?(笑)
④人間洗濯機や未来の生活アイデア展示
1970年の大阪万博では、「未来の生活」を体験できる展示が数多く登場しましたが、その中でも一際注目を集めたのが人間洗濯機です。
これは、パナソニック(当時の松下電器)が出展した「クリーンルーム」で披露されたもので、人がそのままカプセルのような装置に入ると、自動で身体を洗ってくれるという画期的な装置でした。
泡と水流、乾燥まで一連の流れをすべて自動で行うというコンセプトは、「人間も家電で洗う時代がくるかもしれない」と話題になりました。
ほかにも、音声で操作できる家電や、センサーで開く自動ドア、調理ロボットなど、今でこそ見慣れた機能がすでに発想されていたのです。
こうした展示は、「家事を減らして自由な時間を作ろう」という、現代にもつながるライフスタイル提案の始まりでもありました。
本当に、発想がすごいですよね…!今のIoT家電は、当時の夢を現実にしたものなんだなって感じます。
⑤太陽の塔に込められた「生命」のメッセージ
大阪万博といえば、やっぱり太陽の塔。
岡本太郎がデザインしたこのモニュメントは、単なるシンボルではなく、「人類の進歩と調和」という万博のテーマそのものを体現する芸術作品でした。
塔の外観には、三つの顔が描かれており、「未来」「現在」「過去」を表現。それぞれが人間の時間軸を象徴し、「過去を振り返り、現在を見つめ、未来を信じる」というメッセージが込められています。
内部には「生命の樹」と呼ばれる展示があり、生命の進化をたどる構造になっていました。
単に未来の技術だけを見せるのではなく、「人間の原点」にも立ち返る――それが大阪万博の本質だったのかもしれません。
私は初めて太陽の塔を見たとき、その圧倒的な存在感に震えました…!あれこそ、日本が世界に誇れるアートだと思います。
⑥大阪万博の食文化が生んだグルメの記憶
1970年の大阪万博は、技術や展示だけでなく、食文化の面でも数々のブームを生み出しました。
たとえば、前述のブルガリアヨーグルトだけでなく、ケンタッキーフライドチキンが日本初出店を果たし、来場者にアメリカの味を届けたのもこのときです。
さらに、マレーシア館のスパイスたっぷりのカレー、エルサルバドル館の火山コーヒー、アメリカンパークのサンキストジュースなど、世界の本格的な料理を一度に味わえるのは万博ならではの醍醐味でした。
来場者の中には、「缶コーヒーを初めて飲んだ」と記憶している人も多く、UCCが提供した甘い缶コーヒーは当時の風物詩となったようです。
また、世界のグルメを求めて11回以上来場したファンもいたとのことで、万博が「食の冒険の場」でもあったことがわかります。
今でこそ当たり前の「世界の味」が、当時は未知の体験だったんですね~!
これってもう、グルメ万博だったんじゃ?(笑)
⑦1970年の熱気が2025年にも受け継がれる理由
1970年の大阪万博が「伝説」として語り継がれている最大の理由は、その熱気にあります。
当時の日本は高度経済成長の真っ只中で、テクノロジーも経済も、社会も上向き。人々の心に希望と活気が満ちていました。
そうした時代背景の中で開催された万博は、「未来への扉を開く場所」として、6400万人もの人々を魅了したのです。
このエネルギーは、展示物や建築だけでなく、企画・設計・表現方法などあらゆる面に反映されていました。
そして、2025年の大阪・関西万博も、そうした精神を引き継ぐイベントとして、いま再び注目を集めています。
「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマのもと、今度は命、医療、サステナブルを軸にした展示が展開される予定です。
太陽の塔を見た子どもが、未来の展示を作る大人になっているかもしれない――そんな時代のバトンが、再び大阪で手渡されるわけですね。
私も2025年の万博、絶対行きたいと思ってますよ~!あのときの熱気を、今の時代で感じてみたいです。
1970年の大阪万博をきっかけに広がり実現した現代の暮らしのまとめ
1970年の大阪万博は、技術だけでなく文化やライフスタイルにも大きな影響を与えました。
スマートフォンやビデオ通話の原型、ピクトグラム、ブルガリアヨーグルト、回転寿司など、現代では当たり前となったものの多くが、この万博をきっかけに広まりました。
また、動く歩道やエアドームといった建築技術、ウォシュレットや電波時計、LANなども、未来の生活を支える重要な要素として当時の会場に登場しました。
さらに、ファストフードや缶コーヒーといった食文化も、万博を機に広く認知され、日本の食卓や日常に根付いていったのです。
こうした「未来を提示する場」としての役割は、2025年の大阪・関西万博にも受け継がれています。
より詳しく知りたい方は、大阪万博記念公園公式サイトや関西電力メディアページもチェックしてみてくださいね。